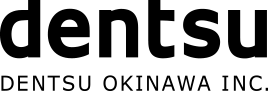SOLUTISON PRODUCE DEVISION
SOLUTISON CREATIVE DEPERTMENT
ソリューション・プロデュース本部 ソリューション・クリエーティブ部

ソリューション・クリエーティブ・本部長
ソリューション・クリエーティブ・本部長
大阪府出身/電通関西支社、東京本社を経て→
2018年電通沖縄に赴任

部長
部長
大阪府出身/2001年電通沖縄に入社

シニア・クリエーティブ・マネージャー
シニア・クリエーティブ・マネージャー
兵庫県出身/大阪でCM制作ディレクターを経て→
2020年電通沖縄に入社

沖縄県出身/2018年入社
「ソリューション・クリエーティブ部」とフルネームで言う人はほぼおらず、「そりくり」と呼ばれるこのチーム。クライアントのあらゆる課題に対して、クリエーティビティを武器に、ベストソリューションを導き出すのが彼らのミッションだ。コロナ禍の中、新戦力を迎え、さらなる新しい課題に取り組む「そりくり」に、仕事の醍醐味を訊きました。

QUESTION.
ソリューション・クリエーティブ部とは、どんな仕事をするところですか?

Hさん 「課題があれば解決法がある」ということで、それを見つけるチームです。広告からその周辺領域まで、アイデアが必要な仕事を全部やっています。イベント企画・実施や映画プロモーション、マーケットリサーチ、コンサルティングまでなんでもありです。このチームは2018年に立ち上がった部署なのですが、フレッシュな戦力も増え、多様な人材が揃っています。
QUESTION.
2020年入社のBさんはどういう経緯で電通沖縄に入社したのですか?

Bさん 僕はこれまで大阪のCMの制作会社で制作業務やディレクションの仕事をしていました。前職では、企画の骨格がある程度できた時点から関わってCMをつくるということをしていたのですが、仕事を続けていくうちに、企画全体に関わりたいなと思いはじめ、就活をして、2020年に電通沖縄に入社しました。入ってすぐリモートだったのですが、最近少しずつ、打ち合わせの時に集まれるようになって、だんだん慣れてきたという感じです。仕事は、民間も自治体も両方に関わらせていただいています。
Bさんはどういう戦力になりそうですか。
Hさん まだ一年目ですが、Bさんはすでに制作側として培ってきた経験がある。とはいえ、同じ「CMをつくる」という仕事でも、これまで違う方向から見てきたことを、今度は電通側がしていたことにチャレンジしているわけで、ベテランのところとフレッシュなところの両方があるんですね。それがいいんですよ。 うちは、新人でも任せられることが圧倒的に多いと思います。小さい会社の小さな部署で、4人しかいないので、現場でやりながら成長してほしいと思っているんです。プレッシャーもあるかと思いますが、新入社員でも若いうちに現場経験がたっぷりできるというのは、地方拠点にいる大きなチャンスだと思います。

QUESTION.
2018年入社のSは、現在、どのような仕事をしているのですか?

Sさん 私はマーケティングの仕事をしています。一年目の時は、いろんな案件に関わってはいてもそれぞれのサポートが中心でした。いまはどんどん意見を言ったり、自分が主体となって関わることが増えていきています。
Hさん Sさんは、ストラテジー・プランナーという、電通沖縄では、過去にはいたけれど、いまは唯一の存在なんです。先輩がいない悩みもあるだろうし、いない分、社外や内地から吸収していこうという気概を感じます。
ストラテジー・プランナーとはどういう仕事なのですか?
Sさん 営業やクライアントが持っている課題やコンペがある時に、課題を解決するためのクリエーティブの表現に持っていく前のアイデア、戦略を考えることが主な仕事です。実際に調査してターゲットを決めて戦略を立てる場合もあれば、いま世間で何が流行っているかとか、世の中の動きを自分なりに解釈して、これがいいんじゃないかと提案をしていくんです。とはいっても、人数が少ない部署なので、一人で、というよりは、みんなで会話したり、共有して議論して積み上げていくということが多いです。
この仕事には広い視野が必要だと感じます。私自身、好奇心が旺盛で、いろんなことを知ったり、いろいろなところに行ったりするのが好きなので、自分に合った仕事だと思っています。

QUESTION.
このチームで手がけられた仕事を具体的に教えていただけますか?

Fさん 「肝高の阿麻和利(きむたかのあまわり)」という、うるま市で長く続いている現代版組踊の舞台があるのですが、電通沖縄はここ10年ほど、少ない予算で、しかし、できうる限りのオーバークオリティでその活動を支える仕事を続けてきています。その「肝高の阿麻和利」の企画演出や脚本をしている団体「TAO Factory」が、2017年、久米島に、史実を元にした現代版組踊「月光の按司(あじ)~笠末若茶良(がさしわかちゃら)」をつくったんです。
そもそもなぜこの舞台を久米島町が立ち上げたかというと、久米島は人口減少が著しく、そのポイント・オブ・ノー・リターンを越えているんです。これから人口が減り続けるという中で、町として、教育委員会として、できることがないか、と考えた時に、島への愛を持った若者が育っていってくれることを望み、この舞台がつくられたそうです。その舞台の2019年の公演のポスターを電通沖縄で制作しました。それがその年の沖縄広告賞のグランプリを獲得。これまでムービーやプロモーションでのグランプリはあったのですが、ポスターでグランプリを獲ったのは初めてで、つくった自分たちでも驚きでした。
どのようなビジュアルのポスターだったのですか?
Fさん 「肝高の阿麻和利」がそうであるように、「笠末若茶良」も地元の中高生が出演するのですが、ポスターにも舞台に出演する子どもたちに出てもらいました。子どもたち3人に本番さながらの演技をしてもらって、カメラマンにできるだけ近寄ってもらって、子どもたちの演技の中での表情に迫るポートレイトを撮ってもらいました。舞台の迫真の演技をポスターで表現するために、全部削ぎ落としました。実際、スタジオの奥でカメラを至近距離で向けられながらも、やりきる強さ、そして、彼らの舞台にかける想いがものすごく凝縮されたポスターになったと思います。つくづく、沖縄の子どもたちの力って本当にすごいなと感じた仕事でした。

ポスターにはどんなコピーがついているのですか?
Fさん 若茶良が亡くなったのが16、7歳と言われていて、舞台もその年齢に近い子どもたちが演じています。なので、コピーの中に年齢は絶対に入れようと思いました。それともうひとつ、この舞台が悲劇なので、その年齢からもっとも遠い言葉を組み合わせたいという想いがありました。それで、コピーライターと相談して、「14歳、運命を悟る。」「17歳、とどかぬ祈り。」「16歳、心を鬼に。」という3つのコピーをつけたんです。 ポスターが総合グランプリを受賞するのは初めてでしたが、審査員も満場一致でこれを選んでくれたというのが驚きであり、嬉しかったですね。もっと沖縄の子どもたちが、沖縄の社会にパワーを与えられるような、そういう機運が高まればいいなと思います。
QUESTION.
他にも印象的な仕事はありますか?
Hさん ここにいる全員で取り組んだ「Be.Okinawa」の最新版です。というのも、2020年はコロナ禍で「沖縄に来てね」と言えない状況でした。「来てね」と言えない、ではどうするか、ということで、毎年来てくれる人に想いを馳せてもらおう、というアイデアが出てきたんです。同時に、沖縄を擬人化するならば、今年は「来てね」と言えないけれど、「元気にしてるかな」と「都会でちゃんと深呼吸してるかな」と、沖縄は思っているはずだと考えました。その双方向の「想いを馳せる」という企画にしようとムービーをつくったんです。
「Be.Okinawa」は観光事業ブランドとして2013年に立ち上がって、それからずっと電通沖縄で手がけさせていただいている、もっとも重要な仕事のひとつです。2018年は安室奈美恵さんの引退と重なり、安室さんからの沖縄への感謝という形で、無償で楽曲が提供されるというすごい出来事が起きました。そして、2019年はラグジュアリーな沖縄を味わってもらうような内容を制作しました。このように、毎年課題が変わっていくのですが、年々観光ブランディングとして積み上げてきた流れを、2020年はコロナで一旦ストップせざるを得ず、「来てね」と言えない中で、どうしようか、と、非常に難しい課題に取り組み、先ほどのテーマに辿り着いたんです。
全員で取り組んだということでしたが、そのプロセスを教えてください。
Hさん チーム全員で沖縄の魅力とは何か意見を出し合ったり、また、同じく沖縄に生まれ育ったSさんがコピーをつくってみたらどうなるのかと挑戦してみたり、FさんとBさんはメインチームではなかったけれど、要所要所で見てもらって、思いつかないような意見を言ってもらったりしました。また、うちの社員で東京に出向してた女性がいるのですが、彼女はBe.Okinawaの立ち上げメンバーでもあり、まさに東京から沖縄に毎日想いを馳せている人。その彼女に響かないと意味がないと思い、彼女にも意見を聞いたりしながら、最初に決まったのが、「あなたの居場所が、ここには ある」というタグラインでした。
音楽は、MONGOL800のキヨサクさんのソロユニット「UKULELE GYPSY」の楽曲を使っています。これは、Sさんが、ふと「この曲が似合うんじゃないか」と提案したことがきっかけとなりました。キヨサクさんにも楽曲提供いただくことが決まり、音楽軸を主体に、行きたいけれど行けない沖縄への想い、来てほしいけど来てと言えない沖縄の想い、というものを、つくりあげていきました。
ところが、途中でコロナの空気が変わって来たんです。つくりはじめた4月、5月の頃は「来ないでほしい」だったのが、仕上がりかけた9月末から10月頭は「気をつけて来てね」という空気になった。そうすると、最初の企画だと、県の最近の方針と食い違っていくので、映像も音楽も出来上がっていたのですが、急遽、コピーをもう少しポジティブに開発しようということになりました。それも含めてこの仕事は大変な仕事でしたが、それこそまさに電通沖縄の腕の見せ所。本当はこうつくったんじゃなかったんだけど、あたかも最初からそうだったように見せる、ということが、チーム全員が関わってつくりあげることで、非常にうまくいったんじゃないかと思います。
QUESTION.
新型コロナウイルスによって、様々なコミュニケーションのあり方や人の動き方も変わってきていると思いますが、
これから、クリエーティブのあり方はどう変化していくと思いますか?

Fさん いま、コロナ禍で、先が見えない時代だと思うのですが、クライアントやつくり手の方々と話していて思うことは、一番自分たちが大事にしていたものは何だろうと、そこに立ち戻るというか、そこしか頼るものがなくなっている感覚があるんです。誰もが答えを持っていないからこそ、自分の存在意義だったり、自分たちが持っている本来のものがキーになってくるんじゃないかと思います。それがぶれていけばぶれていくほど、何をやっていいかわからなくなっていくと思うんですね。
その意味で、クリエーティブも本質に一度立ち戻らなければいけないと思っています。SDGsの実施にしても、それがポーズではなく、自分たちの本来持っている力や意義がSDGsに合致していかなくては、どんどん透明性の高い社会になっていく時に、見透かされてしまいます。そうならないよう、強い力を持たせる、骨太な方向に向かわざるを得ないという気が個人的にはしています。
Hさん それともうひとつ、コロナで、仕事のプロセスが大きく変わったんです。例えば、Be.Okinawaはクオリティを求める仕事なので、東京の制作会社と連携してつくっているのですが、いつもなら東京に出張に行って打ち合わせをするわけです。それが今年はコロナで出張ができないので、全部リモートでやるでしょ。そうすると全メンバーがリアルタイムで共有できるので、僕らが何に悩んで、何に困って、どういう解決策をどう探っていくかという、これまでやっていたことを初めて見てもらえることができたんです。実際に会って話せないストレスもありましたが、それを上回るメリットがありました。電通グループ全体で取り組まなくてはいけないという意識がすごく高まりましたし、リモートでつながる、プロセスやソリューションをシェアできる、ということは、今後、いち地方でものづくりをしていく上で大きな強みになると思います。
QUESTION.
そういう時代において、ソリューション・クリエーティブ部では
どんな人材が必要だと思いますか?
Fさん いままで知見として持っていたことを信用しすぎないということが大事だと思います。新しい感性や新しい知見がものすごく重要になってくる時代になると思いますから。いつもHさんが言うんですが、だからこそ、一人ではなく、チームで闘うことだったり、チームを越えた越境力だったり、面となってこのチームが強くなっていくことが大切になっていくと思います。
Hさん 越境力というのはもっとも大事なことだと思いますね。クリエーティブなり、マーケティングなりの専門の深い知識や経験は必要ですが、クリエーティブだったら、プロモーションやメディア、PR、デジタルの領域のことも勉強して、全部語れるようになる、そういう越境力を持ってほしいんです。Fさんはもともとグラフィック中心だけど、CMも他の統合的なこともやるし、Sさんも戦略を考えるのが本職だけど、コピーも書けば、企画も提案する。それぞれのやる気さえあれば、本業はもちろんだけど、隣と隣の隣くらいまでいって、やれるようになるくらい、成長できるんです。
QUESTION.
電通沖縄だからこそできる、
クリエーティブの面白さとは何だと思いますか?
Fさん 「つくるもの」ということで言うと、クライアントはもちろん沖縄の社会、業界に、いい影響を与えられるものづくりをと、心がけています。沖縄らしさってなんだろう、沖縄のクリエーティブってなんだろうということを、いつも考えていますね。やはり沖縄は、独自の文化圏を持っていますし、県民性にも特徴がありますから、そこで生まれてくるCMもやっぱり独自のものでないと、と思うんです。沖縄の人の人生観や死生観は県外とは違いますから、そういうところをベースに生まれてくるものをつくる、ということがすごく楽しいんですよ。そういう人たちと一緒にものをつくったり、そういう人たちに依頼されてものづくりをしたり、そういう人たちの課題に解決を探していきたいです。沖縄愛、ですよね。
Hさん 「沖縄のために何ができるか」は全員が思っていて、一番大事なところです。当然、東京でいいとされる表現と、沖縄でワクワクする表現は違うと思うので、そこを見極めたいですね。また、「そりくり」だからこその仕事のスタイルで言うと、大阪人が3人いるということもあって、打ち合わせも笑いがあった方がいいし、雑談やアホな話をしながらやっていけるようなことを大事にしているんです。雑談して、仲間がどんな空気で過ごしているかをわかった方がいい。大きな家族みたいな目線でないと、うまくいかないと思っています。笑っているところからいいアイデアが生まれますからね。